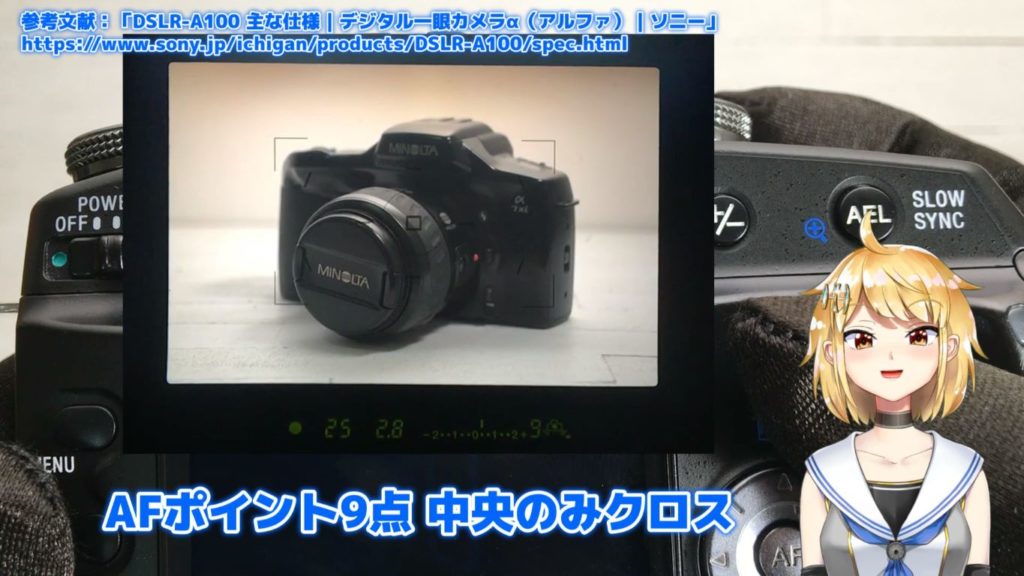みなさんこんにちは。
フィルムカメラ系VTuberの御部スクラですが、今回はデジタルカメラについての動画です。
SONY α100について話します。
Contents
SONY α100のスペック
レンズマウント:Aマウント
センサー:有効画素数1,020万画素 総画素数1,080万画素
シャッター:縦走りフォーカルプレーンシャッター B、30秒~1/4000秒、シンクロ速度1/160秒
露出計:多分割測光・中央重点平均測光・スポット測光
フォーカシング:TTL位相差検出方式(AFポイントは9点、中央のみクロス)
電源:専用リチウムイオン電池 NP-FM55H
発売年:2006年
発売時価格:オープン価格
製造元:SONY
参考文献:
「DSLR-A100 主な仕様 | デジタル一眼カメラα(アルファ) | ソニー」
https://www.sony.jp/ichigan/products/DSLR-A100/spec.html
「Sony α (アルファ) | DSLR-A100」
https://www.sony.jp/products/Consumer/AMC/body/DSLR-A100/
SONY α100について
SONY α100は、2006年に発売したデジタル一眼レフカメラです。
コニカミノルタから一眼レフのαシステムを継承したSONYが最初に発売した機種ですね。
デジタル一眼レフと2006年という年
さて、この2006年という年。
デジタル一眼レフカメラというものが、もともと写真が好きな人以外に広まった年だと思うんですよ。
2006年に発売したデジタル一眼レフというと、α100のほかには、CanonのEOS Kiss Digital X、PENTAX K100D、Nikon D40。
どのメーカーも、だいたいこれくらいの年代から、詳しくなくてもある程度迷わずに使える性能や操作性、サイズ感がデジタル一眼レフに備えられるようになったと感じています。
ただ、その後の時代のデジタルカメラを知っていると、まだまだ性能的に発展途上だと感じるところも多いのですよね。
では、性能や機能についてみていきましょう。
SONY α100の性能、機能
SONY α100は、最初に話したようにSONYがAマウント用のものとして最初に発売したデジタル一眼レフカメラ。
マウントはミノルタαと同じAマウントです。
2006年の機種ということですでにデジタル一眼レフ専用の設計になっていて、ミラーやスクリーンはAPS-Cサイズのセンサーに合わせた小さいものになっていますね。
レンズはミノルタAマウントの各種のものが使えます。
今回はMINOLTA AF MACRO 50mm F2.8を取り付けて撮影してきました。
イメージセンサーは1,020万画素のCCD撮像素子。
参考文献:デジカメWatchより 中村文夫「【新製品レビュー】ソニー α100」
https://dc.watch.impress.co.jp/cda/review/2006/07/10/4174.html
コニカミノルタ時代のデジタル一眼レフカメラ同様、センサー側を動かすCCDシフトによる手振れ補正を備えています。
(上画像、Super Steady Shotが手ぶれ補正のオンオフ)
また、ちょうどこれくらいの年代のデジタル一眼レフから広まった機能だと思うのですが、アンチダスト機能もついています。
手振れ補正の時代
さて、この手振れ補正。
いまとなっては当たり前の機能になっています。
たとえばiPhoneのカメラで写真や動画を撮っても全然手ブレしないことからもわかるように、スマホ等に組み込まれたものを含めて、さまざまなカメラに普通に搭載されていますね。
そんな手振れ補正ですが、このα100が発売した頃って、ユーザーが大歓迎する新機能だったと思うんです。
そもそも、デジタルカメラというのは2000年代後半まで、そこまで高感度に強いものではありませんでした。
わたし自身、2000年代にコンパクトデジタルカメラを持って旅行に行って、手振れ写真を量産していた記憶があります。
で、手振れ補正自体はフィルムカメラの時代から存在した技術だったわけですが、本当の意味で一般ユーザー、つまりカメラに興味がないユーザーまで降りてきたのって、デジタルカメラが普及してからだと思うのですよね。
なぜそうだったのか考えたことはなかったのですが、もしかすると、手振れしていることがすぐにわかるようになったこと、そして、パソコンの大きな画面(スマホはまだなかった)で見るようになったので、フィルム写真のプリントよりもブレに気が付くことが増えたことが理由かもしれません。
いまとなっては忘れがちですが、2000年代中頃までのデジタルカメラのセンサーって、感度の面でもノイズの面でも、ダイナミックレンジの面でもフィルムとどっこいどっこい、場合によってはフィルムの方がまだ勝っていたくらいだったんですよね。
α100のセンサーと感度
それでは、このα100のセンサーって、感度を上げるとどんなもんなのでしょうか?
順番に見ていきます。
ISO100
まず、ベース感度のISO100のとき。
まあ普通です。
拡大しても全然問題ありません。
ISO200
次にISO200。
こちらも画質に引っ掛かるところはないですね。
ISO400
ISO400。
まあ、普通かなと思います。
拡大するとすこーし、微妙なノイズっぽさが出てきていますね。
ISO800
さて。
ISO800。
ここから急に厳しくなるんですよ。
いま、縮小した画像を表示していますが、この時点で黒っぽい部分がかなり怪しい状態になっているのがわかるかと思います。
拡大してみるとこの通り。
ノイズで相当ざらざらです。
いま、デジタルカメラで撮影するときってISO800とか1600くらいなら、よっぽど画質を重視しない限り普通に使ってしまうと思います。
でも、2006年とかそれくらいの時点では、画質を考えると常用できるのはISO400くらいまで、というのが正直なところだった気がするんですよね。
ISO1600
最後にISO1600。
これが最高感度になります。
この縮小画像の時点で、正直、かなり無理をしているのがわかると思います。
拡大するとかなりきついです。
本当にこれは、画質が悪くてもいいから撮れていてほしいというときのための設定だと思います。
ということで、各感度ごとの画質を見てきました。
高感度耐性がぐんぐん上がる時代
2006年のカメラということで、これくらいの高感度耐性なのは仕方ないと思います。
でも、たった2年後くらいにCMOS撮像素子のカメラが広まると、デジタル一眼レフは急激に高感度に強くなっていくのですよね。
わたしがリアルタイムで使っていたその年代のカメラというとNikonのD90(2008年)ですが、ISO1600は普通に使えて、ISO3200も多少のアラを我慢すれば全然鑑賞に耐えうる画質だったと記憶しています。
もちろん、このα100の年代のデジタル一眼レフでも、デジタルの高画質な画像が得られるという大きなメリットがあって、それだけですでにフィルムのカメラに勝っていたわけですが、本当の意味、つまり感度やダイナミックレンジといった面でデジタルカメラがフィルムカメラに完璧に勝ったのは、CMOS素子が一般化したタイミングだったんじゃないかと思っています。
Lo80とHi200
さて、ダイナミックレンジという単語が出ましたが、やっぱりこの時代のデジタルカメラって、白飛びや黒潰れしてしまうことが多かったのですよね。
そこでこのα100には、感度設定のメニューに、シャドウ部分の潰れを抑えるLo80と、ハイライトの白飛びを抑えるHi200という選択肢が備わっています。
Lo80
Lo80だとこんな感じ。
背景の白が飛んでいる代わりに、たしかに被写体の黒部分のトーンが出ていますね。
Hi200
Hi200ですが、こうして普通のISO200と比べてみると、こっちはちょっとわかりにくいと感じました。
感度設定方法
感度の設定自体は、カメラの左手側に上面にあるダイヤルをISOに合わせて、中央のFnボタンを押すと背面の液晶で設定することができます。
ホワイトバランスやフォーカス位置など、その他の設定も同じように呼び出せます。
このあたりの操作については、さすが2006年のカメラだけあって十分に洗練されていますね。
たった4年前のFinePix S2 Proでは感度切り替えがかなり不便だったので、この時代のデジタルカメラの改良のスピードはすごいな、と感じます。
ファインダー
次にファインダーです。
AFポイントは9点。
中央のみクロスということですね。
参考文献:「DSLR-A100 主な仕様 | デジタル一眼カメラα(アルファ) | ソニー」
https://www.sony.jp/ichigan/products/DSLR-A100/spec.html
ファインダーですが、APS-Cサイズのカメラなので、さすがにファインダーが狭く感じます。
といっても、わたしが普段フィルムカメラばかり使っているのも理由なのですけどね。
ペンタミラーが劣化する?
さて、ここからは残念なお知らせです。
画像を見てすでに気づいた方もいるかもしれないのですが、ファインダー視野の上部がうっすらと、赤みを帯びた感じに曇っています。
このα100のファインダーはペンタプリズムではなくペンタミラーを使っているのですが、残念ながら、MINOLTA α-Sweet系の機種と同様、α100のファインダーも変色するみたいなんですよね……。
α-Sweetの黄変が報告されるようになったのがだいたい2010年代中頃。
ということは、このα100が発売してから、現在2022年までだいたい同じくらいの年数が経過したことになります。
最近、オールドデジカメという単語が使われるようになっていますが、初期のSONY製αを使うことができるのはあと少しなのかもしれないですね……。
スタイリング・その他
そのほかの点についても。
全体的なスタイリングは、なんとなく未来的な感じに仕上げられています。
初期のミラーレスのEマウント機も未来的なイメージでしたが、わたしはSONYのそういう方向性のデザインは好きです。
α7の初代もあれはあれで好きです。
外装ですが、グリップは多少経年変化しているようで、ミノルタαのようにボロボロにはなっていないですが、少し膨張? して、本来の位置より少し出っ張ってしまっているようです。
プラ製の外装とツラが合っていません。
あと細かいところとしては、ミノルタαと同じように、電源を切ったときにレンズが無限遠に収納されるのはいいですね。
背面液晶の見やすさは時代なりです。
当時の水準としては十分に大きなサイズの液晶を搭載しているのですが、2.5型、約23万ドットということとで、その後の液晶が急速に高精細になっていったので、2020年代の目から見ると見劣りします。
まあこのへんの感想は後出しになってしまうのですが。
メディアはコンパクトフラッシュを使います。
無理にメモリースティックを使えるようにしなかったのは逆に偉いと思います。
作例
今回撮影した写真を流していきます。
レンズはMINOLTA AF MACRO 50mm F2.8です。
だいたい35mmフルサイズ換算で75mmくらいの画角での撮影になっています。
まあ、この時代のデジタル一眼レフということで、普通に写らないはずがないんですよね。
とくに珍しいことはない、普通の写真という感じです。
でも、2006年の視点に立ってみると、これってすごいことだったんですよね。
カメラさえ買えば、誰でもこれくらいの高精細な写真を撮ることができる。
当時、カメラに興味がない人が持っていたコンパクトデジタルカメラやガラケーに内蔵のカメラと比べると、はっきりいって相当な高画質です。
しかも、さっき高感度やダイナミックレンジがまだまだ発展途上だったといいましたが、同じ時代のコンパクトデジタルカメラに比べれば十分にダイナミックレンジが広く、高感度にも強かったわけです。
ということを考えると、そりゃ2000年代後半、デジタル一眼カメラ(あえて一眼という単語を使います)のブームが起きるわけです。
でも、そういうユーザーが欲しかったのはカメラではなく写真だったんですよね。
もっと小さくて、十分に高画質な写真が撮れるスマホが普及したら、わざわざ単体のカメラを買わなくなるのは仕方ないよな、とも思ったのでした。
まとめ
ということで、SONY α100についてのお話でした。
こうして触ってみると、2006年当時のSONY製カメラというものを追体験できてかなり面白かったです。
ただ、各部に時代を感じる部分があって、ちょっと実用には厳しさを感じました。
これが2008年くらいになると、背面液晶や操作感、レスポンス、高感度耐性といった部分が一気に改善されるので、デジタルカメラにとって2000年代の数年というのはとても大きいのだなぁ、ということを改めて感じたのでした。
ありがとうございました。
御部スクラでした。